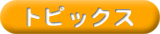■趣旨
集合住宅研究会で継続的に議論を進めている「コミュニティ空間の再考」に関連する各論として、「現代の同居性を巡る専門家の役割・職能」を具体的に議論する。
本研究会では【「つながり」を設計する】をキーファクターとして事業活動を展開する不動産コンサルティング会社の株式会社コプラスの大見卓央氏、大豆生田亘氏、田坂妙子氏を講師としてお招きする。
株式会社コプラスは「事業企画・設計から管理運営までワンストップの事業サポート」といったトータルプロデュースによりコーポラティブハウスを主軸とし、コミュニティ賃貸、コンセプトビレッジ(戸建)等を多数実現している。https://www.co-plus.co.jp/
事業としての仕組みづくり、ファイナンス等お金の流れ、設計手法、運営方法等、実例を通じてご紹介いただくことで、新しいハウジングコンサルタントの役割を探る議論を展開したい。
■開催日時・場所
○令和2年9月8日(火) 18:30〜20:30
※web 会議ツールzoom を活用しての開催
■スケジュール
□趣旨説明 18:30〜18:35( 5分)
□講演 株式会社コプラス 大見卓央氏、大豆生田亘氏、田坂妙子氏 18:35〜19:40(65分)
□休憩 19:40〜19:50(10分)
⬜講師を交えた意見交換・質疑応答
(コメンテーター坂倉建築研究所:今春・日建ハウジングシステム:馬場) 19:50 〜20:30(40分)
■趣旨
日本における集合住宅団地は「昭和」、「平成」に渡り、多くの住まいやまちの社会的課題にも取り組んできた。その中で、コミュニティの意義は常に語られてきた。今日においても、度重なる災害、家族形態の変化、高齢化社会への対応など、様々な局面で集合住宅団地におけるコミュニティのあり方についての議論は多い。コミュニティのポテンシャルを育む空間とはどういう空間であろうか。また、どのような運営方法、維持管理方法が適切なのであろうか。「令和」の時代においても重要な問いかけである。
一方、集合住宅団地の老朽化、人口減少社会に伴う空き家増加などの社会的課題も生まれ、多くの集合住宅団地で持続可能性に関する取り組みが必要となっている。コミュニティのあり方については、団地再編やストック活用を想定した集合住宅団地の持続可能性と合わせて議論していくことが必要であろう。
第356回集合住宅研究会では、「コミュニティ空間を考える(2)」と題し、大月敏雄氏をお迎えし開催した「コミュニティ空間を考える」に引き続き、同様のテーマで、江川直樹氏をお呼びし、集合住宅団地の持続性も含めた「コミュニティ空間」について、実務経験を踏まえた師の考えを通して今後の方向を考えていきたい。
■趣旨
昭和24年「コミュニティへの道」という冊子が当時の建設省大臣官房弘報課から発行されている。冊子の目的は住宅難の解消に向けて団地建設を進めるうえで「都市計画一團地住宅経営」制度の運用の解説書であるが、その前文では、かつて同潤会が建設した分譲住宅地内での空地の活用を通じたコミュニティの発生の状況、そしてこれからの都市型社会における地域コミュニティの意義、有用性が熱く述べられている。
その後70年、日本における集合住宅は「昭和」、「平成」と続いた日本社会において多くの住まいやまちの課題に取り組んできたが、そうした中で「コミュニティへの道」はどのように続いてきたのであろうか。また、これからの新時代、「コミュニティへの道」はどのように続いていくのであろうか。
今日、度重なる災害、家族形態の変化、高齢社会への対応、いろいろな局面でコミュニティの意義は語られている。ではコミュニティの有効化に向けて、空間的にはどのような準備やしつらえが必要なのであろうか。またどのような運営方法が活性化に有効なのであろうか。
令和最初の忘年会を兼ねた研究会のテーマとして、集合住宅の原点ともいえる「コミュニティ空間」を取り上げ、今後の方向を考えていく。
◆スケジュール
10月19日(土)移動日/希望者懇親会
10月20日(日)
(視察1)Binh-Thanh-House(西澤氏事務所兼住居) / 設計・解説:西澤俊理氏
(視察2)集合住宅 / Ly The Dan(リ・テ・ザン)氏 による解説
①CHUNG CƯ NGUYỄN THIỆN THUẬT(グエン・ティエン・トァット・アパート)
②CHUNG CƯ NGÔ GIA TỰ
③Hào Sĩ Phường(ハオ・シー・フゥオン・アパート)
(視察3)black canal / Ly The Dan(リ・テ・ザン)氏 による解説
(懇親会)「ピザ フォーピース」 / 設計:西澤俊理氏
10月21日(月)
(視察4)Apartment in Binh Thanh(ビン・タン・アパート) / 設計・解説:佐貫大輔氏
(視察5)sda(佐貫氏事務所)
(視察6)Wind & Water Café(見学/昼食) / 設計:ヴォ・チョン・ギア・アーキテクツ
(視察7)Green World Kindergarten / 設計:ヴォ・チョン・ギア・アーキテクツ
◆参加者:36名(法人会員14事務所-34名、個人会員-2名)
■テーマ
「高さ制限とは―その成り立ちと超高層化、そして魅力ある都市景観の形成に向けて―」
■趣旨
建築基準法は、前身とする市街地建築物法制定まで遡ると、今年で創設100 年となる。都市計画との関係が密接な集団規定の中でも、建築ボリューム関する規定をみると、集合住宅の計画・設計にたずさわる私たちにとって、直面する課題が多いのではないだろうか。建築基準法緩和による競争力激化は、限られた枠組みの中での居住空間の確保という命題をより難解にしつつある。一方、行き過ぎた緩和を抑えるためにも、観光立国に向けた諸施策の背景からも、高さ制限や景観コントロールに関わる諸規制が導入されつつあり、設計環境はさらに複雑化している。
大澤先生のご講演を通じ、形態規制の成立が、どのように超高層化につながっていったのか、それがどのように評価され、将来どうあるべきなのかを把握することは、課題の解決にとどまらず、より良い都市環境の形成にために大きな知見が得られると思う。
一方、法実務運用の立場として金子氏からは、超高層建築が前提とする建築基準法の特例的運用や、法運用において「制限と実況の乖離」が顕在化しやすい日影規制からみた高さ制限の課題等について、ご講演いただく。
高さ制限の系譜と成果・課題の考察を通して、その役割・意義を活発に議論したい。