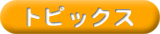■趣旨
少子高齢化、人口減少が進んでいる中、日本の総世帯数は増加している。それに伴い住戸数も増加しているが、住戸総数が世帯数を上回る状況が続いており、今後総世帯数が減少に転じた場合、住宅ストック数は更に増えていくことが予想されます。
時代の変化や街の変化、人々の考え方、生活スタイルの変化に追いついていない住宅が多く見受けられ、単に修繕するのではなく、その場所の街として何が求められ、どのようなニーズがあるかを元に考えていく必要があります。
公共へ開いた住宅づくり、街に開いた住宅づくり、外に向けて開いた住宅としていくことで、人と街とのコミュニティツールを増やし、地域コミュニティを活性化させ、街の魅力アップによる持続可能な街づくりになえると考えます。そこで今回は周辺地域から人が集まり新たな賑わいをもたらすリノベーションについて、ブルースタジオの大島芳彦氏を講師としてお招きし、これからのリノベーションのあり方について視野を広げて考えたいと思います。
■開催要領
◇日時 令和3年9月13日(月) 18時〜20時10分
◇場所 ①web参加(配信場所:市浦ハウジング&プランニング会議室)
②現地参加(コロナ禍のため数名程度限定で募集)
■スケジュール
(1)趣旨説明 担当幹事 18:00〜18:05(5分)
(2)講演 ブルースタジオ 大島芳彦氏
テーマ:「集合住宅のリノベーションによる地域コミュニティの活性化(前半)」 18:05〜18:50(45分)
(3)休憩 18:50〜18:55(5分)
(4)テーマ:「集合住宅のリノベーションによる地域コミュニティの活性化(後半)」 18:55〜19:40(45分)
(5)講師を交えた意見交換、質疑 19:40〜20:10(30分)
コメンテーター:奥茂謙仁氏(市浦ハウジング&プランニング)
■趣旨
新型コロナ・パンデミックは、都市にヒト、モノ、カネが集積することの危うさを露呈し、グローバリズム偏重の社会システムに警鐘を鳴らしました。今年度の当研究会では、アフターコロナの「共同居住と集合住宅」をひとつの視点にあげていますが、その解題にあたっては、在宅ワークや在宅学習を含む住宅・住宅地の多機能化の要請といった顕在化しているテーマにとどまらず、改めて、現代の社会システムの中での住宅・居住のあり方を考えることからはじめたいと考えます。
そこで、今回は、住宅・居住と市場、社会などとの関係性について、我々の専門領域とは異なる社会学の観点からの示唆を、東京大学大学院の祐成保志准教授よりいただいた上で、今後のあり方についての議論を試みたいと思います。
■開催要領
◇日時 令和3年7月9日(金) 18時〜20時
◇場所 ①web参加(配信場所:市浦ハウジング&プランニング会議室)
②現地参加(コロナ禍のため数名程度限定で募集)
■スケジュール
(1)趣旨説明 担当幹事 18:00〜18:05(5分)
(2)講演 東京大学大学院人文社会系研究科 祐成保志准教授
テーマ:「居場所の未来を考える」 18:05〜19:05(60分)
(3)休憩 19:05〜19:15(10分)
(4)講師を交えた意見交換、質疑 19:15〜20:00(45分)
コメンテーター (株)市浦ハウジング&プランニング 川崎 直宏
(株)ディーワーク 古林 眞哉
■趣旨
高齢化と人口減の進展、家族形態や生活様式の多様化に加え、COVID19 感染予防の面から人と人との触合いが回避される中で、地域コミュニティの存在自体が問われている。
今から10年前に発生した東日本大震災では、津波と原発過酷事故により広域的、長期的に居住者の避難が余儀なくされた。避難所、応急仮設住宅、高台移転や復興住宅へと転居が繰り返され、元来人口減と高齢化によって地域の活力が失われている中でコミュニティの喪失に拍車がかかった。別の見方をすれば、被災地固有のものと されて内在していた課題が、将来的に都市部でも起こりうる課題として一気に先取りされて顕在化したともいえる。
被災地の復興のために数々の取組がなされたが、それがどのような意義をもち、どのような課題をもたらしたか。東日本大震災発災10 年を迎え、地域コミュニティのあり方の面からそれを検証したい。
なお、今回の研究会は日本建築学会建築計画委員会のメンバーも参加するコラボシンポジウムとします。
■開催日時・場所
◇日時 令和 3 年 3 月 10 日( 水 ) 18 時〜 20 時 30 分
◇場所 市浦ハウジング&プランニング会議室+ ZOOM
■スケジュール
◇趣旨説明 18時〜18時05分(5分)
◇講演1 18時05分〜18時50分(45分)
研究者の立場から「津波と原発事故による復興計画のパラダイムシフト 」
東京大学都市工学科特任教授 窪田亜矢先生
◇講演2 18時50分〜19時35分(45分)
設計者の立場から「岩沼市玉浦西災害公営住宅 B 1 地区と石巻市北上町にっこり団地災害公営住宅の計画を通して」
都市建築設計集団/UAPP(仙台市) 手島浩之氏
休憩 19時35分〜19時45分(10分)
◇講師を交えた意見交換 19時45分〜20時30分(45分)
・設計者の立場からのコメンテーター
ディーワーク 藤沢毅氏(宮城県内の復興、女川町の高台移転等を担当)
・研究者の立場からのコメンテーター
名城大学教授 高井宏之先生(日本建築学会住宅計画小委員会 メンバー)
・参加者
■趣旨
昨年度の研究会において連続2回開催された「コミュニティ空間を考える」では、自然災害の多発や家族形態の変化、人口減少・少子高齢化社会など大きく変容する社会状況に対する課題を踏まえ、団地再編やストック活用を想定した集合住宅団地の持続可能性を見据えながら、現状抱えるコミュニティ空間の課題や計画事例をご紹介いただき議論を行い、知見を深めてきた。一方この連続研究会を踏まえて集合住宅研究会では、自主研究会として「コミュニィ空間研究会」を立ち上げ、引き続きコミュニティ空間の事例収集や体系的な整理を通してコミュニティ空間のあり方を研究するところにある。
こうした背景とともに昨今のコロナ禍を通して見えてきた働き方のあり方や暮らしへの影響という新たな社会的な課題が生じている状況を鑑み、今年度においても同様のテーマに新たな視点を踏まえ、更に深堀した議論を展開したいと考え、千葉大学名誉教授小林秀樹先生をお招きし、長年のご研究をもとに、とりわけ「生活領域」に関する研究を通してコロナ禍の今後の暮らしの変化を見据えたコミュニティ空間のあり方について講演いただき、我々集合住宅設計の専門家として、これからの集合住宅の計画におけるコミュニティ空間のあり方を考えていきたい。
■開催日時・場所
2020 年12月18日(金) 17:30〜19:30(120 分)
建築家会館及びweb(zoom)開催
■スケジュール
(1)趣旨説明担当幹事 17:30〜17:35(5分)
(2)講演小林秀樹千葉大学名誉教授
テーマ:集合住宅計画におけるコミュニティ空間のあり方
WITH コロナ時代の暮らしの変化を踏まえて
17:35〜18:45(70 分)
(3)休憩 18:45〜18:55(10 分)
(4)講師を交えた意見交換会
司会・進行 川崎 直宏(市浦H&P)
会場及びweb からの質疑(休憩時間までに頂いた質疑)等
18:55〜19:30(35 分)
■ 趣旨
多様化し、変化していく家族構成や働き方、それに合わせて変化していく住まい方に伴い、住宅へのニーズも多様性を増している。一方で住宅ストックが飽和状態にある中、市場価値をいかに向上させ提供していけるか、その手法に期待が高まっている。
そんな中、我々が集合住宅を計画するにあたって重要な要素の一つとなる照明計画や色彩・サイン計画について、その専門性の高さから意図した通りにいかなく、いかにしてアプローチしていくか悩まされることが間々ある。特に建物の改修の場合においては既存建物やそれを取り巻く環境などの与条件が付加され、新築の場合とはまた異なるアプローチ手法が必要となる。
そこで、本研究会においては照明計画や色彩・サイン計画に焦点を当て、この分野からいかにして建物の価値向上を図っていけるか、実際の改修事例などを題材として、その基礎知識や計画へのアプローチ手法などを改めて学ぶ場としたい。
■ 開催日時・場所
○10 月23 日(金) 18:00〜20:30
○開催場所 Zoom (発信場所:LPA 事務所)
■ スケジュール
□趣旨説明 (日東設計 乾、山設計工房 南雲)
18:00 〜 18:05
《 照明計画 》
□講演1 面出 薫氏(LPA) 『集合住宅の価値を高める光の原則』
18:05 〜 18:35
□講演2 窪田 麻里氏(LPA) 『原則を踏まえた実例紹介』
18:35 〜 18:50
《 色彩・サイン計画 》
□講演3 原田 祐馬氏(UMA) 『色彩計画、サイン計画の手法と実践』
19:00 〜 19:45
□質疑応答(事前募集)
20:00 〜 20:30