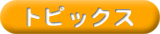■趣旨
日本における集合住宅団地は「昭和」、「平成」に渡り、多くの住まいやまちの社会的課題にも取り組んできた。その中で、コミュニティの意義は常に語られてきた。今日においても、度重なる災害、家族形態の変化、高齢化社会への対応など、様々な局面で集合住宅団地におけるコミュニティのあり方についての議論は多い。コミュニティのポテンシャルを育む空間とはどういう空間であろうか。また、どのような運営方法、維持管理方法が適切なのであろうか。「令和」の時代においても重要な問いかけである。
一方、集合住宅団地の老朽化、人口減少社会に伴う空き家増加などの社会的課題も生まれ、多くの集合住宅団地で持続可能性に関する取り組みが必要となっている。コミュニティのあり方については、団地再編やストック活用を想定した集合住宅団地の持続可能性と合わせて議論していくことが必要であろう。
第356回集合住宅研究会では、「コミュニティ空間を考える(2)」と題し、大月敏雄氏をお迎えし開催した「コミュニティ空間を考える」に引き続き、同様のテーマで、江川直樹氏をお呼びし、集合住宅団地の持続性も含めた「コミュニティ空間」について、実務経験を踏まえた師の考えを通して今後の方向を考えていきたい。
日時:令和2年1月22日(水)18:30〜20:30
第356回研究会について/来年度の研究会テーマについて/建築計画委員会シンポジウムについて
■趣旨
昭和24年「コミュニティへの道」という冊子が当時の建設省大臣官房弘報課から発行されている。冊子の目的は住宅難の解消に向けて団地建設を進めるうえで「都市計画一團地住宅経営」制度の運用の解説書であるが、その前文では、かつて同潤会が建設した分譲住宅地内での空地の活用を通じたコミュニティの発生の状況、そしてこれからの都市型社会における地域コミュニティの意義、有用性が熱く述べられている。
その後70年、日本における集合住宅は「昭和」、「平成」と続いた日本社会において多くの住まいやまちの課題に取り組んできたが、そうした中で「コミュニティへの道」はどのように続いてきたのであろうか。また、これからの新時代、「コミュニティへの道」はどのように続いていくのであろうか。
今日、度重なる災害、家族形態の変化、高齢社会への対応、いろいろな局面でコミュニティの意義は語られている。ではコミュニティの有効化に向けて、空間的にはどのような準備やしつらえが必要なのであろうか。またどのような運営方法が活性化に有効なのであろうか。
令和最初の忘年会を兼ねた研究会のテーマとして、集合住宅の原点ともいえる「コミュニティ空間」を取り上げ、今後の方向を考えていく。